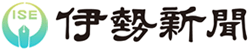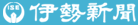▼「一子」と書いて「いちこ」と読ませる友達がいた。学校でからかわれ、幼い頃この名前が大嫌いだったそうだ。成人して気持ちが変わった。個性的な名に愛着が増して親に感謝するようになったという
▼漢籍から引用した立派な名前を学生時代に平凡な「二郎」に変更した知人がいた。「難しくて正確に読まれない」という家庭裁判所への申請で、不許可理由になる「親が付けた名前が嫌なため」をクリアした
▼他人のことでなく、我が子の命名には苦労した。専門家に依頼したら「けい」の字が入るのがいいという。兄弟の子に「圭」があったので、次善の字を選んだら、第二子の時、再び「けい」を薦められた。二度の返上も恐れ多く、漢字を「景」に、読み方を「きょう」にした。担任が替わるたびに「ちゃんと呼んでくれない」と言われ、「個性的でいいんだ」と強弁したが、少し胸が痛んだ
▼第一子も、学校で命名の理由を発表することがあり、問われて「次善の名に」とも言えず、胸が痛んだ。かくゆう自分も、幼い頃嫁しゅうと戦争が激しく、我が名はしゅうとが付けたと母が悔しそうに言うのを聞いて、名前が好きになれなかった
▼かつて「悪魔」という名を子につけて社会問題になったことがあった。「子どもの福祉を害する可能性がある」という市役所の不受理理由はもっともだが、言葉は生き物。歴史上の人物などは正確に読めないことも多い
▼法務省が氏名の指針を発表した。「一般に認められているもの」との指針はともかく、具体例などは不用な気がする。