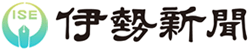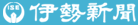三重県は28日の地籍調査推進検討会で、地籍調査のペースを高めるための「取組方針」を策定した。事前防災の観点から優先的に進める区域を選定。技術面で市町を支援するための会議を設けることも定めた。進捗(しんちょく)率が「全国最低レベル」とされる県内の地籍調査を加速させたい考え。
県によると、県内は地籍調査を終えた比率を示す「進捗率」が10%で、全国との比較では46位。全国平均の53%を大幅に下回っている。年間の進捗も0・1%程度にとどまっている。
進捗率が低い理由として、県は市町の人員不足や予算が十分でないことなどを挙げている。市町の担当者は平均で1・7人。年間予算は平均で約1858万円程度という。
これを受けて県は昨年7月、野呂幸利副知事を座長とする地籍調査推進検討会を設置。3回にわたる課長級職員の会合や各市町への聞き取りなどを経て、方針を取りまとめた。
方針は地籍調査のペースを上げるための方向性として、効率的で円滑に推進できる体制の整備や強化▽優先的に推進する区域の選定▽迅速に進める重要性の周知―を掲げた。
具体的には、県や市町などでつくる「地域連絡会議」を九つの地域ごとに設置。市町の事務負担を軽減するため、民間への包括委託や航空機測量をはじめとした先進技術の活用を促す。
また、人員や予算を有効活用するため、地籍調査の必要性が高い区域を独自に設定。津波浸水想定区域や土砂災害特別警戒区域などを参考に、29市町の計380平方キロメートルを設定した。
この区域でも、現状の進捗率は34%にとどまっているという。県は地籍調査の必要性が高い区域の地図データを市町に提供するなどし、優先的に進める区域を決めるよう促す方針。
この日の会議で、野呂副知事は「能登半島地震によって地籍調査の重要性が改めて確認された」とした上で「方針に基づいて取り組みを進め、進捗も確認してほしい」と指示した。