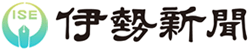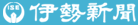三重県が注力する取り組みの一つが「プロモーション」。歴史や自然、食といった魅力を生かし、三重県という地域そのものの認知度を高めることで、観光の振興や移住の促進などにつなげる狙いらしい。
県は昨年度以降、プロモーションの司令塔となる推進本部を設置したほか、取り組みのよりどころとなる推進方針を策定。プロモーションの本格的な展開に向けた土台づくりを進めてきた。
そのプロモーションで軸となるのが「美し国みえ」というキャッチフレーズ。推進方針と合わせて昨年5月に決定した。先月には、このキャッチフレーズを表現したロゴマークも発表した。
県は令和7年度の一般会計当初予算案で「プロモーション推進事業」の費用に約4400万円を計上。このキャッチフレーズを活用し、東海道新幹線の車内広告などで統一感のある情報発信を進めるという。
ただ、このキャッチフレーズが決まった過程が見えにくい。有識者に検討を依頼したわけでもなければ、かつての観光キャンペーンで実施したような公募もなかった。聞けば「庁内で検討して決めた」らしい。
折しも、一見勝之知事は「強じんな美し国三重」を掲げて初当選し、その後は県の長期計画の名称に「美し国」を採用。担当者はキャッチフレーズ選定を巡る「知事への忖度」は否定したが、唐突感は否めない。
一方、県庁内からは「美し国」を使うことに疑問の声も上がる。ある県職員は「そもそも『うましくに』と読むことさえ、あまり知られていないのでは。外国人に意味を説明するのも難しい」と指摘する。
「美し国」の意味を十分に発信しているとも言い難い。ロゴマークへの県民投票を呼びかけたチラシには「三重県は海や山の豊かな自然に恵まれ、人が暮らすのに理想的な地域として、古くから美し国と呼ばれてきた」とあるだけだ。
「実はそれ、ぜんぶ三重なんです!」や「つづきは三重で」など、これまでも県には複数のキャッチフレーズがあった。ただ、新たな物が生まれては、古い物が消えるの繰り返し。継続性は感じられない。
県の担当者は「美し国」について「日本書紀にも記述がある」と主張するが、現代でも通用するかは別の話。キャッチフレーズの意味が十分に理解され、県外にも浸透を図れるか。県の手腕が問われよう。