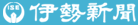フランスのシエルブールへ行きかけたことがあります。29年も前のことです。25歳の頃でした。ヨーロッパを一人で旅していた私は、シエルブールへとパリから鉄道に乗り込んだのです。
北フランスにあるこの港町は第二次大戦時、カレー、ノルマンデイーと並ぶ連合国軍上陸候補地点でした。各国の情報機関が上陸地点を探ってしのぎを削ったようです。戦後、数多くのスパイ小説がこれらの土地を舞台に発表されました。「針の眼」などのすぐれた小説もそのひとつです。結果的には、連合軍は後者に上陸したのはご承知のとおりです。
なぜ訪れようとしたのかと自問してみますと、一度だけ見た映画「シエルブールの雨傘」の影響だったに違いありません。
1964年公開のこの映画は、全てのせりふが歌になっている、という破天荒なものでした。その映画はミュージカルなのですかと、尋ねられることもあるのですが、いわゆるミュージカルとは言い難いのです。何故ならダンス(踊り)のシーンがいっさい無いのですから。
優れて音楽的であるといわれるフランス語でなければ、こんな映画つくりは不可能だったでしょう。この素晴らしい映画を拙い文章で解説する無粋さ、愚かさを、お許しください。映画離れしている若い世代の方が、これを契機にご覧になっていただければ、という勝手な思いに免じてご寛恕いただければ幸甚です。
映画は3部構成になっています。
第一部 出発
1957年11月のこと、物語は町なかにある自動車修理工場に、ベンツが滑り込むところから始まります。工場主の残業要請を断って、傘屋の娘ジュヌビェーブ(カトリーヌ・ドヌーブ)とのデートに急ぐ主人公ギイ(ニーノ・カステルヌーボでした。熱烈に愛し合う二人ですが、ギイに召集令状が来ます。2年間の兵役義務をフランス国に課せられたのです。
「 2年も会えなくては、生きていられないわ。」と身も世も無く、嘆き悲しむ金髪、涙に濡れた美貌の19歳のカトリーヌ・ドヌーブは一時代を画しています。
その夜二人は結ばれます。 ギイが指定された軍隊駐屯地へ旅立つ朝の駅頭、見送りにきていたジュヌビエーブは「Mon’amourモナムール(私の恋人よ)。生きている限り待っているわ。」と流麗なフランス語の歌で台詞を語り、固く抱きしめ合います。
「これでお別れだ。行かなきゃ。僕を見つめないでくれ。」
「ジュヌ・セ・パ(そんなことできないわ)。」と飛びついて再び抱きつくジュヌビエーブでした。
いつものように、バーバリーのレインコートを着ているジュヌビエーブは、ポケットから青いスカーフを出して胸元で握りしめたままです。
「モナムール(愛しい人よ)」と出て行く列車のデッキに立つギイは呼びかけ、ジュヌビエーブは、「ジュ・テーム、ジュ・テーム(愛している)」と叫び続けます。
ミシエル・ルグランの主題曲も素晴らしく、形影伴い、ここで映画の前半の最高点に沸騰します。
映画のコンテ割の妙というのでしょうか、カメラに向かって進んでくるギイの乗った列車が画面の左側に、立ち尽くしたまま小さくなっていくジュヌビエーブのベージュのレインコートと青いスカーフが真ん中に、列車の進行に連れてカメラは後退していき、屋根のない駅のホームに立つ横長の看板が、画面の右の上端にすこしずつ文字が現れてきます。
手前側からはホームを海軍将校がヒロインの方に歩いていきます。こちら側に徐々に速度を上げてくる列車。まんまん中には立ちすくむジュヌビエーヌ。右側には歩んでいく水兵。音楽が最高潮に達し、列車はスピードをあげ、ジュヌビエーブが米粒の如く小さくなったとき、「CHERBOUR(シエルブール)」と駅名が掲げられているのです。
三十年(みととせ)の昔、私はこの看板を見たいと思ったのでした。
駅には別離の悲しみがあります。別れの悲しみに蹲っている(うずくまっている)魂魄(こんぱく)や、諦めきれず、はしゃぎまわって宙を飛び回っている精神が存在します。
再会の喜びもあるのですが、悲しみの魂のほうが多く、さ迷っているように思うのは私だけでしょうか。
第二部 不在
1957年12月。税金の督促状が来て、店が差し押さえられることになったジュヌビエーブの母、エムリィー夫人(アンナ・ヴェルノン)は亡き夫が買ってくれた思い出の宝石を売ることにしました。母娘二人が訪れた宝石店主は、うちで買う事は出来ないから買う人を探してあげようと言います。
「前金だけでも、もらえませんか。」と困惑する夫人を拒む店主。恥ずかしさと絶望でその場に昏倒しそうになった夫人であり、その体を支えるジュヌビエーヌです。その店に宝石の卸に来ていて居合わせた、フロックコートにネクタイを締めた、高級宝石商の青年紳士が「その宝石は私が買いましょう。」と申し出ます。「パリかロンドンですぐ売れます。」と。ジュヌビエーブの美貌に惹かれたからでもあります。映画の冒頭に、ギイの勤めるガレージにベンツを乗り入れたローラン・カサール(マルク・ミシェル)です。
1958年1月。ギイからの便りはありません。ギイの子を孕んだ(はらんだ)ジュヌビエーブはギイを全面的に信じています。カサールは彼女との結婚をエムリー夫人に申し込みます。
1958年3月。ギイからの便りは依然としてありません。ジュヌビエーブの心は少しずつカサールに開かれていきます。彼はお腹の子もひきとるというのです。
1958年6月。ジュヌビエーブとカサールは結婚します。教会から出てきた二人を乗せたベンツが立ち去り、それを見送る叔母の親族マドレーヌでした。
第三部 帰還
1959年3月。ギイはアルジエリア戦争で負傷して除隊してきました。足が不自由になっていた彼は、ジュヌビエーブが結婚したことを病床の叔母から聞きます。叔母は死に、ギイにすべて残すと約束してくれていたなにがしかの遺産で、結婚したマドレーヌとギイはガソリン・スタンドを買います。
1962年12月。雪降るクリスマス・イヴ。マドレーヌは息子フランソワと玩具屋にプレゼントを買いにガソリン・スタンドを後にします。ベンツが給油に停まり、ミンクのコートを着たジュヌビエーブが運転席に、助手席には女の子が座っていました。エムリー夫人は亡くなり、彼女はパリに住んでいるといいます。「貴方に似ているわ。会って見る。」と言うジュヌビエーブに「もう行った方が良い。」と言うギイでした。
ベンツは走り去り、同時に母子がクリスマス・プレゼントを抱えて雪の中を転がるように、ガソリン・スタンドに走りこみます。
ベンツがガレージに入るところで物語が始まり、走り去るところで終わります。映画の途中何度も各シーンの露払い役をベンツが務めています。例えば、「カサールさんがみえるから待っていなさい。」という母親の制止を振り切って傘店を飛び出した娘が下手(しもて)に走ると上手(かみて)からベンツがゆっくり登場して停車する場面。ギイに会いに修理工場へと横断しょうとする道を通過していくベンツというシーンでは、ベンツ走り去る、ギイが自転車を引いて修理工場から出てくる、駆け寄るジュヌビエーブ、が寸分の狂いも無く進行しています。このドイツ車がカチンコの役をこなしている感があります。
映画の一糸乱れぬ動きは、糸で操られたマリオネット(人形芝居)の如き心地がしてなりません。「われ等は人形で人形遣いは天さ。ひとしきり演技を済ましたら、もとの小箱に収められるのさ。」と詠ったのはトルコの詩人でしたが、この映画の人形遣いは監督ジャック・ドウミーです。映画史に残る大傑作を一作だけ残しましたね。うらやましい限りです。
戦争を扱った映画ですが一発の銃弾も発射されません。爆発も殺人もありません。悪人が一人も出てきません。しかしこれはまぎれも無く反戦映画です。けだし、二度の大戦で多くの人命を失ったフランス人は、重く深く戦争を捉えているのでしょう。
「吹き抜けのない住宅を設計してみなさい。」と言ったのは故吉坂隆正早大教授です。一人の死者も出ない反戦映画も、困難なプロジエクトであったでしょう。作り手の力量が問われますし、ハッピーエンドではないですから、ハリウッドでは作れない映画です。ここに日本映画のひとつの道筋があるようです。「草原の輝き」もハッピーエンドでは無かったですね。
ようやくこの文章を完成することが出来ました。次の映画についての文章はいつだといわれ始めてから2年半が経ちました。あるとき、私の携帯電話に「シエルブールの雨傘」のテーマ・ミュージックがピアノで弾かれて添付メモで、送られてきたことがありました。それからも1年以上書くことが出来ませんでした。いろんなことを思い出すもので。
ところで、三十年前は結局シエルブール駅に着くことは出来ませんでした。道中いろいろありまして。
生きているうちに、訪れる機会はありやなしや。